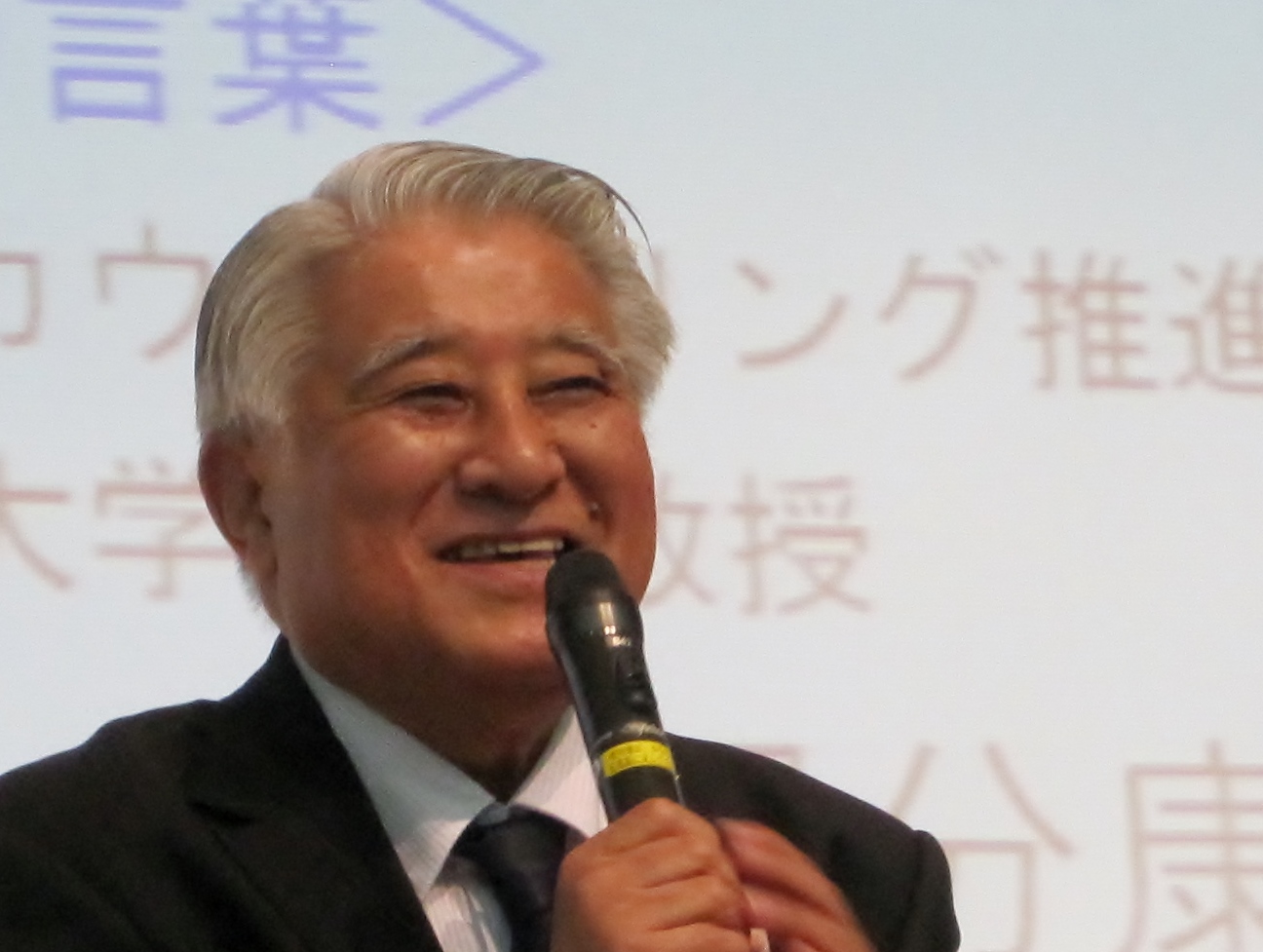沿 革
当協議会設立までの背景
- 1990年5月
- 日本カウンセリング学会が「学校現場において生徒指導・教育相談・学級経営などの分野で指導者的立場から指導及び助言を行えるものが設置されるべき」という考えから,日本教育心理学会・日本進路指導学会(当時)に「学校機関における『相談指導教諭(仮称)』制度新設」を呼びかけ,両学会はこれに応じた。以来3学会が連携し,実現に向け検討を行った。
- 1997年
- 上記3学会が、文部省中学校課に「養護教諭が児童生徒の身体の擁護をつかさどるように,心の問題を担当し,また子どもたちの適応的・進路的相談指導をつかさどるもの」として「相談指導教諭(仮称)」制度の新設案を提示(1/15付)した。しかし、実現には至らなかった。
〇スクールカウンセリングに関する諸団体の動向
スクールカウンセリング諸団体では「カウンセリング心理士;旧認定カウンセラー(1986年)」「キャリアカウンセラー(1992年)」「学校カウンセラー(1995年)」「学校心理士(1997年)」「臨床発達心理士(1997年)」「教育カウンセラー(1999年)」などの資格認定が行われ,それぞれに活動していた。 これらの資格は,文部科学省(旧文部省)のスクールカウンセラー事業における任用規定では,スクールカウンセラーに「準ずる」者とされていた。そこでこれら資格の認定機関や学会の中には,文部科学省に対し,これらの資格取得者について正規のスクールカウンセラーとして扱ってほしい,「準ずる」という扱いを改善して欲しいと要請するものがあり,そのような団体が連合して活動しようとする機運もあったが,各団体の認定する資格が消滅してしまうのではないかという不安から話はまとまらなかった。文部科学省から「同じ考えを異なる団体が個別に訴えるのではなく,窓口が一つにならないか」という提案があった。この提案を受け,6資格の認定機関とそれを支持する学会・団体が「(各資格が相互扶助して共存する)緩やかな連合」というコンセプトを共有して,2009年に「スクールカウンセリング推進協議会」(2015年4月に一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会に移行)が設立され,この連合の認定資格として「ガイダンスカウンセラー」を創設した。
当協議会設立以降
- 2009年5月25日
-
國分康孝を発起人に「スクールカウンセリング推進協議会」設立。
國分康孝が初代理事長に就任。「スクールカウンセリング推進協議会設立趣旨」
2009年5月25日
学校教育に役立つ「子どもたちの発達課題を解き成長を援助するスクールカウンセリング」を,有効に機能させるために参加団体が協力する。発達課題とは,子どもたちの①学業,②人格形成・社会性,③進路,④健康面の発達を指す。これらに対して,すでに発生した問題に対する個別面接だけでなく,予防・開発的に,教室での集団指導や学校組織でのチーム対応,教師へのコンサルテーションなど多様な方法を用いて,学校教育の充実に資することをめざす。
- 2010年1月13日
- 文部科学省児童生徒課・岸田室長の助言を受け,SC推進協議会として一つの資格が作れないかという協議が始まり,統一名称とし「ガイダンスカウンセラー(GC)」を採用。
- 2010年4月7日
- 文部科学省児童生徒課・岸田室長と國分康孝代表・石隈利紀・村主典英がスクールカウンセラーの資格に関する会合で「ガイダンスカウンセラー」創設に合意。
- 2010年9月27日
- 第11回理事会でガイダンスカウンセラー資格審査規程承認
- 2011年9月22日
-
第3回認定委員会を経て、ガイダンスカウンセラー資格認定を呼びかける
「ガイダンスカウンセラー資格認定試験呼びかけ文」
2011年9月22日
学校教育に役立つ「子どもたちの発達課題を解き,成長を援助するスクールカウンセリング」を有効に機能させるために参加団体が協力してガイダンスカウンセラーの資格認定試験を実施します。
発達課題とは,子どもたちの①学業面,②進路面,③人格形成面,④社会性の育成面,⑤健康面の発達を指します。これらに対して,すでに発生した問題に対する個別面接だけでなく,予防・開発的に教室での集団指導や学校組織でのチーム対応,教師へのコンサルテーションなど多様な方法を用いて,学校教育の充実に資することをめざしています。
- 2011年10月16日
- 第1回公開シンポジウム「教育の再生と創造の原動力」(於跡見学園女子大学文京キャンパス)を開催。以降,毎年開催(2021年を除く)
- 2011年12月26日
- 構成団体有資格者のガイダンスカウンセラー審査を開始。
- 2012年10月14日
- 第1回ガイダンスカウンセラー資格認定試験実施
- 2015年4月1日
-
「一般社団法人日本スクールカウンセラー推進協議会」として登記。
「『スクールカウンセリング推進協議会』の法人化(一般社団法人)にあたっての趣意書」
2015年2月27日
学校教育の主たる内容は学習指導と生徒指導である。ところが教員は担当教科については専門教育を受けているが,「居場所のある学級づくり」「ふれあいのある人間関係」「学習意欲の高まるキャリア教育」「問題行動への対応」「通常学級における支援教育」など生徒指導の分野については,教科教育ほどにはプロフェッショナルとは言いがたいのが実情である。
そこで,学校教育に役立つ「子どもたちの発達課題を解き成長を援助するスクールカウンセリング」を有効に機能させるために,カウンセリング関係の資格認定6団体を含む9団体が協議して「スクールカウンセリング推進協議会」を平成21 年(2009年)5月に立ち上げた。ここでいう発達課題とは,子どもたちの①学業,②進路,③人格形成・社会性,④健康面の発達をさす。これらに対してすでに発生した問題に対する個別面接だけでなく,予防・開発的に,教室での集団指導や学校組織でのチーム対応,教師へのコンサルテーションなど多様な方法を用いて学校カウンセリングの充実をめざしている。
これまで任意の団体として約6年間,「スクールカウンセリング推進協議会」は,文部科学省や都道府県・政令指定都市の教育委員会に対し,スクールカウンセラーの差別なき採用と待遇を求めて運動を行ってきた。埼玉県やさいたま市など一部において運動の成果は現れているものの,まだ全国的には差別が続いている。そこに任意団体としての限界があるのも事実である。このたび,法人格を得て本協議会の社会的評価を高めることにより,任意団体の限界を突き破りスクールカウンセラーの差別の改善に前進し,ガイダンスカウンセラー資格や構成団体の資格の質や量の向上にいっそう取り組む。さらに中・長期的目標として,カウンセリングに加えコーディネーターの資質を備えた,道徳教育および生徒指導・進路指導を計画的に推進する核となる,スクールカウンセリングの常勤教諭(仮称「相談指導教諭」)の創設に力を注ぐものである。
- 2015年4月
- 東京都教育庁指導部高等学校教育指導課が「定時制高校中退予防対策事業」立ち上げ,早稲田大学河村茂雄研究室に講師派遣等の依頼をした。その後,本協議会が主体となり事業を8年間継続した。2023年度からは,東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課「都立高校生の社会的・職業的自立支援教育プログラム事業」に移行して,対象を定時制以外にも広げている。
- 2020年10月
- 文部科学省より「スクールカウンセラー等活用事業に関するQ&A」が公表され,「Q3.スクールカウンセラーの選考に当たり,必要な資格はありますか。」の回答に,ガイダンスカウンセラーが,「⑤都道府県又は指定都市」が認める場合の例として示された。
- 2021年3月
- ガイダンスカウンセラー・スーパーバイザー資格ならびにガイダンスカウンセラー・シニアスーパーバイザー資格誕生